こんにちはちゅーりーです。2023年4月にIT系国家資格の基本情報技術者試験に合格しました。
(科目A:710点、科目B:745点)
このブログでは基本情報技術者試験の合格を目指す方に向け、科目A、科目Bの対策、CBT試験の特徴や注意点について3回に分けて解説していきます。
- 仕事や家事育児で時間がなく、効率よく基本情報技術者試験に合格したい人。
- ITパスポートや情報セキュリティマネジメント試験に合格し、次のステップを狙っている人。
基本情報技術者試験について
IT系の国家資格はIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)という組織が主体となっており、ITパスポートのような一般ビジネスマンを対象とした基本的なものから、アーキテクチャやネットワークスペシャリストのような専門家を対象としたようなものまで、各レベルに応じた13個の資格が用意されています(2022年12月時点)
 ちゅーりー
ちゅーりーどれにしようかなー・・
 ウォンバ
ウォンバ選べるほど余裕ない・・
数あるIT系の国家資格の中でも基本中の基本かつ有名なのが基本情報技術者試験ではないでしょうか。この資格を取得していればIT技術者として基本的な知識・スキルは身についているという証明になります。
ちゅーりーも20年ほど前ですがIT業界に身を置くようになってから「いずれは取得したいな・・・」と思っていたためすごく心残りがある資格でした。
※今はITパスポート試験ができたので、残念ながらそちらのほうが知名度が高いかもしれません。
ちゅーりーはプロフィールにもある通り法学部卒のガチ文系ですが、少なくとも20年IT業界を経験した今なら簡単に取得できるのではないかと思い立ちました。
また、2023年4月より年2回の試験から通年試験に変更となるようなので万が一失敗してもリカバリーがききます。
 ちゅーりー
ちゅーりーIT業界で経験を積んだ今の僕なら・・っ!
 ウォンバ
ウォンバそううまくいかないんだよね・・・
勉強を始めてすぐにその考えは甘かったと思い知らされました。
16進数やネットワーク、アルゴリズムなど改めて学習すると理解できていなかったり、過去無かった新しい情報がアップデートされていたり意外と難しくて大苦戦です。そもそも言葉の意味や解き方を知らないとチンプンカンプンな問題が多いため、試験のための学習が必要となると感じました。
唯一理解できたのは情報セキュリティの章でした。
事前に情報セキュリティマネジメント試験の勉強をしていたのが役に立ちましたが、やっぱりIPAの表の通り徐々に資格のレベルを上げて学習を進めていくイメージなのでしょう。初心者はITパスポート試験を受けてからの受験が無難かもしれません。
科目Aの対策 基礎のインプット
まずは科目Aの対策を考えましょう。基本情報技術者試験は科目A(90分/60問)、科目B(100分/20問)の2部構成となっています。科目Aは基礎的なIT知識を問うもので、科目Bはプログラミングや情報セキュリティの実践、という位置づけです。
いずれも6割(600点/1000点)取れれば合格となりますので、知識を完璧にする必要はありません。
①ある程度日常的にITに関わっている or ②初学者または全くITに関わっていないのいずれかで使用する教材や勉強方法をわけましょう。
①ある程度日常的にITに関わっている
基礎ができているのでなるべく短期間で効率の良い合格を目指しましょう。2か月程度あれば十分合格レベルに達するでしょう。ちゅーりーも1日平均1時間の勉強で2か月(約60時間程度)で合格することができました。そのうち科目Aに費やした時間は40時間程度だったと思います。
おすすめは「出るとこだけ!基本情報テキスト&問題集」です!
正直内容は足りていません。解説も超シンプルです。
細かなシステム用語(カプセル化、アジャイル開発 など)はほとんど含まれておらず、2進数や16進数、線型探索、アルゴリズムなど「普段ITの仕事をしていてもあまり出てこない試験用のシステム用語や計算ロジック」にのみフォーカスした形となっています。
そのためむしろポイントを絞った効率的な学習が可能となっています。このテキスト&問題集を何度も繰り返すことで科目Aの対策は完了です。短期で合格を目指す方には最適!
※シンプルすぎて解説が少しわかりづらいところがあるかもしれません。YouTubeの講義動画やネット検索でカバーしましょう。
また、システム用語についてはノー勉でもある程度対応できると思いますが、付録でついている過去問を数年分解くかネットで重要な過去問を検索して頭に入れておけばOKです。
②初学者または全くITに関わっていない
普段全くITに関わっていない方は基本的なIT用語などから学習する必要があります。ITパスポート試験を受験していればある程度時間短縮可能ですが、学習期間として4か月は見ておいた方が良いでしょう。
テキスト&問題集は上記の「イメージ&クレバー方式 栢木先生の基本情報技術者教室」または「キタミ式 基本情報報技術者」を選びましょう。
両方ともわかりやすくて良い教材ですが、後者の方がイラストが豊富で読み物としても面白く興味を引く内容でより初心者向けな印象です。
前者は処理の動きや数字の変化がよりわかりやすくイメージで解説されており、実習( 手を動かす)しながら理解をしていく形です。
科目Aの対策 勉強方法
勉強方法ですがシステムの試験とはいえ科目Aは暗記の要素が強いため、まずは参考書を回転です。論点やキーワードと問われ方のパターンを覚えて、問題を出されたときに何について問われているかに気付き、解き方を当てはめて回答できるようにしましょう。1か月程度あれば問題ないかと。
そのあとは実際の過去問を回します。基本情報技術者試験試験ドットコムさんの過去問道場で「おすすめ」ボタンを押して年度を絞り込んだら「学習開始」を押して何度も何度も過去問を周回します。
参考書に出てなかった内容があったら解説を読んでインプットしながら進めます。試験前の2週間で3~4周もすれば記憶に定着すると思います。
おまけ
2進数、10進数、16進数の変換
・2進数⇔10進数
2進数各ビットの値を記憶してしまいましょう。あとは各ビットの数に値を掛けるだけで10進数へ変換することができます。倍にしていくだけなのでそこまで難しくありません。
・・・256,128,64,32,16,8,4,2,1
・16進数⇔10進数
Aが10と覚えておけばとっさに10進数へ変換できます。
・10進数⇔2進数
コツは大きなビットから埋めていく、です。10進数10であれば10を超えない一番大きな2進数ビットは8ですので4ビット目に1を埋めて残りは2なので2ビット目に1を埋めます。
・16進数⇔2進数
16進数の各桁を10進数に変換し、その後2進数へ変換でOKです。目安として16進数の1桁は2進数の4ビットで表現できます(16進数の1桁=0~15の16パターン、2進数の4ビットで表現できる数=16パターンで合致するため)
 ちゅーりー
ちゅーりーパターンさえ覚えれば対応できます!
論理演算
わかりづらいのはNAND、NORでしょうか。それぞれANDとORで偽(false、0)となるパターンの時に真(true、1)となります。
XORはいずれかのみが真の時に真となります。ORと違い両方真の時は偽です。
| AND | ・ | 論理積 | 両方 真(true、1)であること |
| OR | + | 論理和 | いずれかまたは両方 真(true、1)であること |
| NOT |  ̄ | 論理否定 | 偽(false、0)であること |
| NAND | | | 否定論理積 | ANDで偽(false、0)となるパターンの時 |
| NOR | +と ̄の組合せ | 否定論理和 | ORで偽(false、0)となるパターンの時 |
| XOR | ⊕ | 排他的論理和 | いずれかのみが 真(true、1)であること |
なお全加算器の問題は回路や構成を覚える必要はなく、インプットを単純に足して繰り上げ数などを計算すればOKです。
 ちゅーりー
ちゅーりー真実は一つ!
データベース
仕事でSQLを触ったことがある人であれば楽勝です。Accessで構わないので一度SQLを実行してみることをお勧めします。
SQL文は特にGroup by がよく出題される気がします。キーとなる項目をGroup by XX,XXで定義し、尺度となる項目をsum(),ave()などで集計します。
わかりづらいのは正規化です。
第一正規形: 重複を省く。
例えば下記の例は顧客に対する「商品の購入数」が重複しているので正規化されていません。
| 顧客番号 | 商品Aの購入数 | 商品Bの購入数 | 商品Cの購入数 |
第二正規形: キーの部分従属性を排除する。
例えば下記は顧客×日付×商品番号がキーのデータですが、商品番号に紐づく「商品名」が存在します。キーの一部に従属する項目が存在しているので正規化されていません。
| 顧客番号 | 日付 | 商品番号 | 商品購入数 | 商品名 |
第三正規形: キーの推移従属性を排除する。
例えば下記の例は社員が決まれば所属組織と住所コードが決まり、住所コードが決まれば住所名が分かるというように推移従属性があるため正規化されていません。
| 社員番号 | 所属組織 | 住所コード | 住所名 |
ネットワーク
とっつきにくいNo.1のネットワークです。
・サブネットマスクは建物名(ホストアドレス)と部屋番号(ネットワークアドレス)、みたいに覚えてください。ホストアドレスはビット数が決まっていて、部屋番号をネットワークアドレスで指定します。
・ネットワークアドレスのビット数を割り出して2進数で指定できるパターン数を計算します。ローカルアドレスとブロードキャストという概念があり指定できるアドレス数は-2とします。
・OSI参照モデル「アプセトネデブ」、超有名ですね。
アルゴリズム
・キュー : 先入れ先出し(先に入れたものを先に出す)
・スタック: 先入れ後出し(後に入れたものを先に出す)
・クリティカルパス: 「一番時間がかかるルート」と覚えましょう。
テクノロジ
・90%の90%は何%: 文系には厳しい問題ですが0.9*0.9の0.81(パーセント)で計算できます。
・分数をパーセント変換: 100を掛ければいいだけです。目から鱗が落ちるとはこのこと。
・MIPS: 10MIPSとは1秒間に10 百万の処理をできる性能ということ。
つまりは数字 × 106の形にしてしまえばそれでOK!
・ミリ秒: これも数字 × 10-3の形にしてしまえばそれでOK!
まとめ
・基本情報技術者試験を取得すれば技術者として基本的な知識は身についていることの証明となる。
・ITパスポート、情報セキュリティマネジメントの上位資格としての位置づけのため、それらを取得してから受験するのが内容も理解しやすくお勧め。
・基本情報技術者試験は科目Aと科目Bに分かれ、それぞれ違った形の対策が必要。
・科目Aはとにかく過去問を回転させて解き方のパターンを覚える。問題を見て素早く何について問われているのか気が付くようにしよう。
・科目Bはプログラムの実際の動きをトレースする問題がメイン。変数の値や参照の動きを丁寧にステップ化して追っていくようにしよう。
・情報セキュリティは情報セキュリティマネジメント試験を受験していれば問題なく解けるはず!
 ちゅーりー
ちゅーりー国家資格の取得は結構うれしいです!
 ウォンバ
ウォンバリベンジ成功だね!
GLMOW!
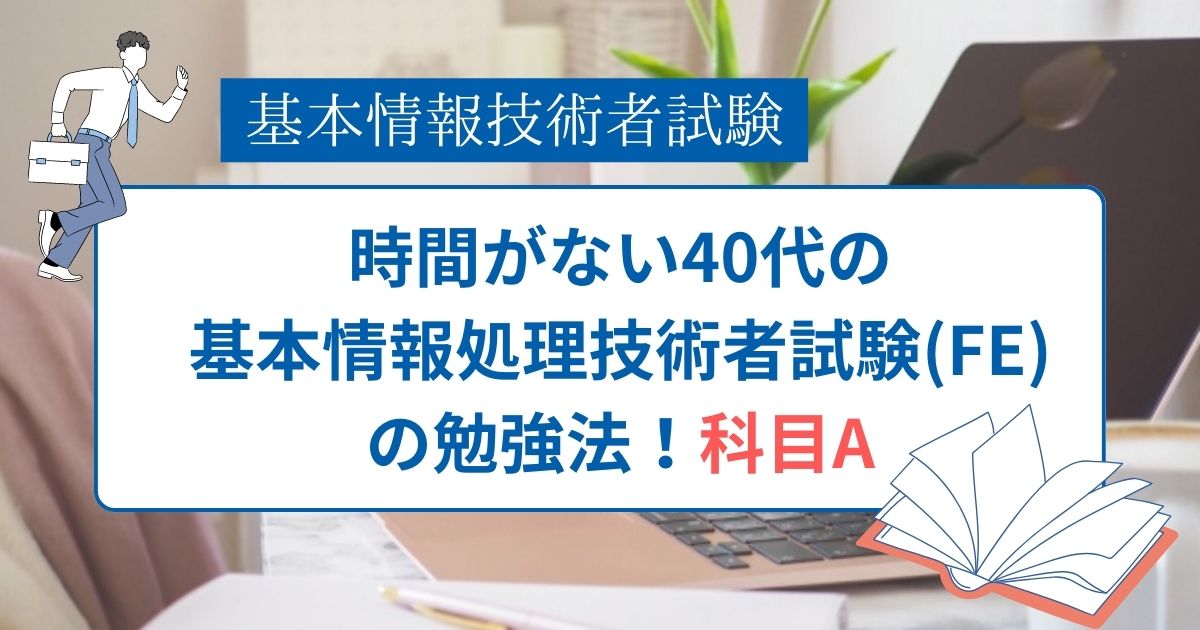

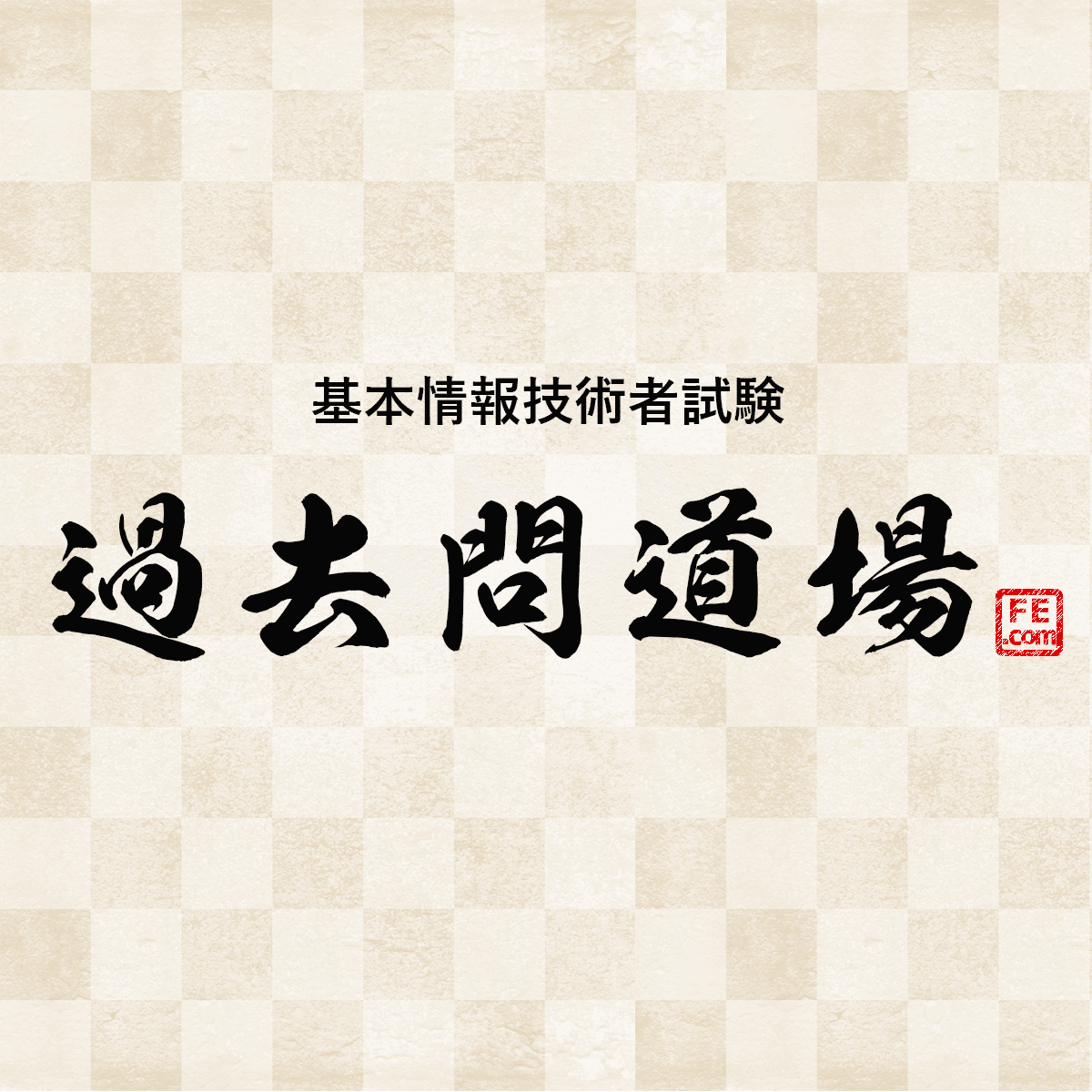

コメント